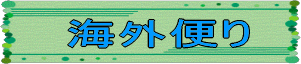 その4
その4 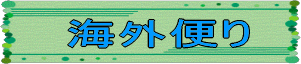 その4
その4 更新 2007年2月6日
小山 様
平素御無沙汰しておりまして恐縮です。
名古屋に本社を置くさるゼネコンの方々が目下当地滞在中で、弊員も昔からの知り合いでもあり、相談に乗っている事情これあり、貧乏暇無しにしています。
さて、御話しのありました、除草剤ですが、現代の農業は有体に申し上げまして、除草剤はじめとする農薬無しでは穀物、果実、の大規模栽培は出来ないというのが実態です。勿論のこと野菜栽培でもこれらは使用されています。日本流に数反の畑を使った箱庭農業ならば成る程除草剤無しでも何とか工夫して作物栽培は可能かも知れません。然しながら、数十、数百、数千ヘクタールの畑に生える雑草を取り除くのは人力、機械力を用いてもやれないことは無いでしょうが、極めて困難と申し上げざるを得ないのが実情です。だからと言って、弊員は除草剤を擁護する立場ではありません。農業は人間が口に入れる作物を栽培する産業ではありますが、一方で経営、即ち採算が取れて初めて何ぼの世界があることも事実です。何百人という労務者を投入して雑草を取り除くことは理論上は可能ですが、実際にやれるかとなるとこれまた話は別でして人夫がきちんと作業をしているかの監督も厄介な仕事となります。畢竟、安全・リスク・採算の微妙なバランスで止むを得ず使用せざるを得まいというのが農業界の大方の良心的な方々の意見であろうと推察します。世界の食糧基地の一つとなっている南米での農業の規模を考慮すると、農薬無しの栽培は到底考えられません。
当国パラグアイは実は世界で5-6番目に位置する大豆栽培国です。第二次世界大戦終了後にパラグアイに移住された日本人農家の方々が当地の気候に合った作物として紹介したのが始まりで、現在は年間に凡そ400万トンを生産し、5-6億ドルの輸出産業(総輸出額の約25%を占める一番の輸出商品)になっています。
時折、弊員のところに無農薬、有機栽培の大豆を手当てしたいのですがという問い合わせがあります。当地でもこれ栽培していない訳では無いのですが、調べてみると生産量は極僅かで日本側の御希望される数量には到底及ばず、然もこの手の栽培農家(残念乍ら日系ではなくドイツ系)は長年に亘ってドイツの特定の顧客の為に、特別のノウハウを用いて栽培しているということも判って参りました。
除草剤を使わなくとも雑草に強い種類を何とか作れないかというので登場したのが、実は遺伝子組み換え作物なのです。
農家の生産コストダウンにこれほど寄与している作物は有史以来ないだろうとさえ南米では言われます。病害虫に強い、雑草に強い、即ち、消毒剤、殺菌剤、除草剤使用を少なくし(完全に不要という訳ではありませんけれども)、消毒・殺菌・除草に掛かる諸般の経費削減に繋がったのです。勿論のこと、一方で遺伝子組み換え作物が人体に安全か否かの議論に決着がついていない現実もあり、まだまだ暫くは試行錯誤が継続するのでしょう。日系農家でも採算面より、遺伝子組み換え大豆を栽培する方々が増えている様です。
エクアドル産のバナナを食べられないという御心配は無用です。過剰反応は禁物です。はっきり申し上げますが、本当に無農薬、有機肥料のみ使用した有機栽培の作物は地上で入手不可能と申し上げても良いくらいです。此の種作物を本当に入手できたとしても価格は十倍どころか数十倍を超えるのは確実です。広い農場を用意して、周囲からシャットアウトし、その中心地を利用して徹底的に手をかけて栽培してこそ、無農薬・完全有機栽培と言えるのですから。
何か水を差すような話になってしまい、申し訳ありません。
申し上げたいのはエクアドルで除草剤被害があるとの報道があってもそれに過剰反応されないことです。マスコミは過剰報道(つい先だっての納豆報道)の性癖がどこにもあります。
勿論のこと、農薬、除草剤は使わないに越したことはありませんが、使わないなら、現在の地上の人口を養うに足りる食糧をどうやって確保するの?という議論が必ず出てきます。
コカ撲滅の為の除草剤の話から些か飛んでしまい失礼しました。
コロンビアの影響を受けるエクアドルもいい迷惑でしょうが、薬剤散布、昆虫・鳥類飛来には国境という人為的な境界線は防止策足り得ないことの現われでしょう。チリは南米諸国の中では文字通り地理的な構造を上手く利用して薬剤・昆虫の近隣諸国からの被害を食い止めていると言えます。ペルーとの国境である北部は砂漠、アルゼンチンとの国境である東部はアンデス山脈、南部は氷と岩、其の向こうはホーン岬、西部は
太平洋に面している陸の孤島とも言えます。
パラグアイは如何に?経済的にブラジル・アルゼンチン両国の影響をもろに受け、病害虫も飛んで来る・飛んで行く、こう申しては実も蓋もありませんが、旦那を二人もった妾で両方にいい顔をしていなければ生きて行けない、風見鶏とでも言いましょうか。(かかる表現に女性の方々から苦情が出ないことを祈ります)
イースター島は御指摘の通り、チリの領土です。チリ駐在中に一度行って見たかったのですが、とうとう果たせずで、残念なことをしました。日本人夫婦が居住しているのは初めて知りました。
日本は立春、梅の楚々とした香りが漂う季節ですね。
伊賀上
2月4日
![]()
パースはここ数日40度以上の暑さが続いており、ひと夏に数えるほどしか使わないエアコンが今はフル回転です。 風があっても外へ出れば熱風。 大抵は湿度が低く、住宅の壁には断熱材が入っているのでエアコンなしでも過ごせる日が多いのですが、やはり40度はア ツ イ!!
この時期のオーストラリアのイベントといえばテニス全豪オープンの開催と1月26日のオーストラリアデーです。
全豪オープンは予想通りフェデラの優勝。 ファイナルで対戦したチリのゴンザレスにガンバッテほしかったのですが、残念。
これからは誰がフェデラを負かすかより、どれだけフェデラがテニスの歴史をぬりかえていくかの方に世間の関心はあるんじゃないかしら。 なんだか朝青龍みたいですね。
さて、オーストラリアデーですが、 これは建国記念日にあたるもので、歴史的には1788年にイギリスのアーサーフィリップ船長率いる第一次移民団が初めてシドニーに入植した日を記念したのが始まりだそうです。
今日では勿論この日は祝日で、国中挙げてのビッグイベントです。
この日の理念はオーストリラリアという国の偉大さを賛美し、オーストリアリア人であることに誇りを持ち、将来より良い国へと更に発展することを誓い、国民一丸となってこれからも頑張りましょうということかしら。
具体的にオーストラリアの偉大さ、誇れるものというのは、まず、国民、そして国土、移民国家としての多様性、原住民の文化、自由と民主主義、それとこの国の社会的モットーとなっているfairness公正さ、mateshipなどでしょうか。
多くの移民者にとって夢でもあるオーストラリア市民権取得のセレモニーや、いろいろな分野で活躍、貢献した人達に授けられる各賞の発表、そしてAustralian of The Yearが選ばれるのもみんなこの日を祝う為のものです。
因みに今年のAustralian of The Yearは、長い間地球温暖化問題を取り上げ、京都議定書に批准していないオーストラリア政府を批判していた自然環境科学者、フラナリー教授が選ばれました。 批判の的であった当のハワード首相から祝福と賞を受け、首相が「教授の受賞はちょうど時を得たもので、国民にこれまでとは違った、新しい環境問題の方向性を考えさせるだろう。 でも教授はいつも政府の政策に賛同してくれているわけではないですね。 でもそんなことは問題じゃない。」というと、教授は受賞の際、しっかりと京都議定書のことの批判も忘れず、「これは私の人生で起こった皮肉な事態のひとつだ。」とのたまう。 これってスゴイと思いませんか。私はこんな時にオーストラリア人のユーモアと寛容性、ふところの広さみたいのを感じます。 これこそfaienessの精神じゃないかしら。
ま、とにかく いろいろ公式な催し物やセレモニーなどが目白押しだけど、このオーストラリアデーは一般的に言い換えれば、愛国心丸出しのお祭りと言った方は分りやすいかも知れません。 国旗を掲揚する家も多く、上に掲げたような理念など知らなくても、若い人達は国旗の模様のシャツや帽子などを身につけたり、国旗そのものを体に巻きつけたり、小旗を手にしたりして、この日の夜に打ち上げられるこの日最大のイベント花火見物にでかけるのです。 とにかくあらゆるところに国旗が見られます。 自国の国旗にあれだけ愛着する様子は多分日本では考えられない光景でしょう。
この花火大会が又スゴイのです。 写真を掲載しましたが、去年はなんとここパースで40万の人が花火見物したとのこと。 今年はこの日は41度あったせいか例年より繰り出した人はグッと少なかったようです。
とにかく、国中で、オーストラリア万歳、オーストラリア人万歳なのです。 日本ではとかく問題になる愛国心が、ここでは純粋に自分の国(自分が生まれた国、又はあとから市民権をとった国)を愛する心なんだって思います。 政治やイデオロギーや宗教などそんなやっかいなものと結びつけずにただ自分の国を愛するって、とっても自然な当たり前のことなんですよね。 だって、自分が属している自分の居場所の原点ですもの。 そしてそういう心を大切に思う社会、フツウに認める社会は見ていて気持ちがいいです。
日本では国旗掲揚と一緒に国家斉唱もよく問題になるけど、ここでは息子たちが通っていた小学校では集会のたびに国歌を斉唱していたし、国内(海外チームとの試合でない)の大きなスポーツ大会の決勝戦の前にも国歌が流れるし、とにかくいろいろな場所で歌ったり聞いたりします。
国歌も国旗と同じでその国の国民なら当然愛着があり愛国心と同じ大切なものだと思うので、日本の学校の卒業式などで君が代を歌う歌わない、日の丸を揚げる揚げないで揉めるニュースを見ると、とてもフシギな気がします。
とにかく毎年この日に感じることはオーストラリアは本当にラッキーカントリーということ。 だって、あれだけ国民に愛されて、祝福されるんですもの。
オーストラリアは国民が愛する、いや愛せる国なんですね。
オーストラリア バンザーイ!!
マグラ-原口節子
 |
 |
|---|
 |
 |
|---|
【管理人】オーストラリアの建国記念日は、ずいぶんとにぎやかなようですね。そして、原口さんがオーストラリアを大切に思う気持ちも伝わってきます。花火の写真はなかなか難しいのですがキレイに取れていますね。有難うございます。
![]()
2007年、もう1月も終わりとなりますが、皆様にとってどのような年の始めとなりましたでしょうか、どうぞ今年はより良い年で有りますように。
1月始め頃まで暖冬といわれ、70度(華氏)の日があり、半袖で外が歩けたNY、ちょっと異常とおもっていましたが、さすがに寒くなりました。金曜日朝は9度、摂氏でいうとマイナス10度位でしょうか、さすがに寒いです。外を歩くときにはコートは勿論ですが、マフラー、帽子、手袋、、、、でも裏の着いた手袋でも15分もすると手の先がかじかんできます。昔最低華氏1度という時がありましたが、空気がぴりぴり、痛いという感じで山でスキーをなさるかたはお分かりかと思います。雪の日は暖かいです。晴れて風があると体感気温が下がるので、とても寒く感じますが、でも、家のなかは暖かいので、コートの暖かい物があれば大丈夫です。
陽があたっていても日中の気温はあまりあがりませんし、最高気温というのが日中に出るということでも有りません。天気図に注意といったところでしょうか。NYは日本の様に一応の四季はありますが、
ちょうどいい気温というのはとても少なく、寒いか暑いか、、、極端で、まるでNYそのものです。
一時少なくなっていたホームレスの人がこの数年また少し増えています。此の時期は凍死することも有るので,市では寒いという予報の時にはそういう人たちをシェルターに収容する努力をしています。地下鉄の中,道の排気口のところなど、に生活用品全てをいれたバッグを持って生活しています、日本でも今、そういう人たちが問題になっているみたいですが、おそらく、一番の違いは、こちらでは、単に経済的な理由ということでは無く、社会的に集団生活ができない人たちということではないでしょうか、一時的にシェルターに収容しても社会生活に適応できないということでまた路上に戻ってしまう、ということです。
今日も此の寒空の中(華氏30度でした)、バスの中から、外を大きなポリバケツを引きながら歩いている人を見ました。上は裸、下は毛布を巻きつけ、足は、両足違う色のソックス、で歩いていました。そして手にはペーパーカップに小銭がはいったものをチャラチャラいわせて歩く姿はさすがに異様で、ちょっと避けて通るという感じです。しかし一般的にはホームレスの人たち、地下鉄で物乞いをする人たちに対して、人々は寛容で
だいたいはポケットの小銭を(せいぜい 50セント、一ドルぐらいまでですが高額の人も、)寄付をしています。教会ではスープなどの提供もあります。
先週、高級アンティークのお店の外にホームレスが住み着いて景観を損ねるということで、裁判を起こすこととなりましたが、紆余曲折あり、其のお店の外に温風が出てくる口が有るのですが、お店の地下のダクトを替えてそこには温風が出ないようにして、温和な解決法ということで裁判を取り下げるということが話題になりました。この人は新聞に載って、縁者がいることもわかりましたが、連絡を取りたくないとの本人の希望でした。
温度の差だけでなく、貧富の差も激しいNYですが、今日本も年金、国民保険等の問題から色々なことがおこりつつ有るようですね,テレビで放映されているのは極端な例なのでしょうか、それとも切実な問題なのでしょうか、、、
実際に暮らしていらっしゃる皆さんはどのように把握していらっしゃるのでしょうか。
12月にお送りしたメールで ご質問の「Love Story」のスケートリンクはセントラルパークです。向こう側に見える建物は今でもあります。スケートリンクは南側から入って割合に近いところにあり、80年台半ばにきれいに改装されて人気スポットです。このスケートリンクは結構映画撮影に使われています。
セントラルパーク ウォールマンリンク
というところで、皆さん、寒い時期 お体にお気をつけてお過ごしください。
【管理人】ニューヨークはこの季節、マイナス10度にもなるのですか。そんなに寒いところとは知りませんでした。Love Storyのスケートリンクの話、有難うございます。ずいぶん昔の映画ですが、ラストシーンは記憶に残っています。日本の年金の話は、私たちにとって、次第に身につまされる身近な話題となっています。風邪を引かないよう、がんばってください。